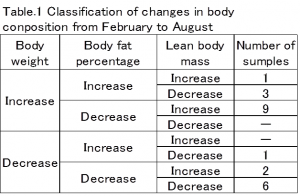王鞍日向(関西大学文学部)
キーワード:東大阪市役所、地域、普及活動
[はじめに]
ラグビーが日本に初めて紹介されたのは、1899(明治32)年、慶應義塾大学のある東京だとされている。関西に移入してくるのは11年後の京都で、大阪に広がるのはさらに9年後の1919(大正8)年といわれている。大阪は東京に20年遅れてのスタートであるにも関わらず、これほど盛んになったことは注目すべき点である。
しかし、ラグビーの普及に関する研究で、地域との関連がみられるものがあまり行われていない。技術論や、けがの防止策についての研究がほとんどであるため、どのような普及の歴史があったのか、見当がつかなかった。
そこで筆者は、ラグビーのまちと呼ばれている東大阪市を対象に調べることにした。花園ラグビー場がある東大阪市は、他の地域と大きな差異があると考えたからである。
[方法]
2010(平成22)年に東大阪市役所内に設置された、ラグビーワールドカップ誘致室の室次長である本園康成さんにお話を伺った。また、東大阪市立英田中学校ラグビー部の山地英之先生にもお話を聞くことができ、練習の様子を見学させていただいた。
[結果]
ラグビーのまちを表明した1991(平成3)年以降と,ラグビーワールドカップ日本大会が決定した2009(平成21)年以降と,大きく2つの転機があったと判明した。
1991年に東大阪市が「ラグビーのまち」であることを表明し、力強さや団結力がイメージできるラグビーを前面にだして政策を進めていくことを決めた。1992(平成4)年には,現在のマスコットキャラクターであるトライくんが誕生した。また同時期から,マンホールや水道仕切弁のデザインにラグビーの絵が施され、ラグビーのまちらしさを感じることができる。
2009年には、2019年のラグビーワールドカップが日本で開催すると決定し、翌年に東大阪市は開催誘致のために誘致室を設置した。市民への認識度向上と開催誘致を盛り上げるため、ラガーシャツやポロシャツの製作、原動機付自転車などのオリジナルナンバープレートの交付、花園ラグビー場周辺でのお祭りなど、様々な視点からラグビーの普及活動にまい進されていることが明らかになった。
また、元日本代表で現京都産業大学ラグビー部コーチの元木由記雄氏や近鉄ライナーズキャプテンの豊田大樹らを輩出した英田中学校では、少なくとも7年前から英田幼稚園とラグビーを通じて交流している。年に2回行われるその交流はトライデーと呼ばれ、園児には楽しみな行事のひとつとなっている。この交流には行政などは一切関わりがなく、英田幼稚園のほうから声をかけたという。同じ校区内という地域のつながりによって実現できる交流は、とても貴重なものであると考えられる。
[おわりに]
市民や子ども達へのラグビーの普及活動を継続し、野球やサッカーに劣らぬ魅力があることを伝えるために、地域の頑張りが不可欠だと感じた。